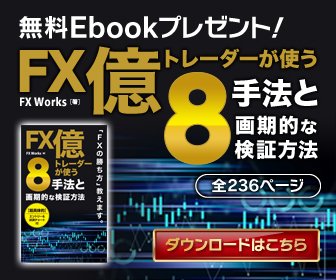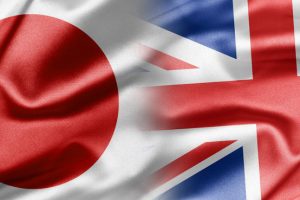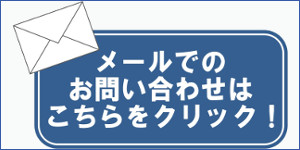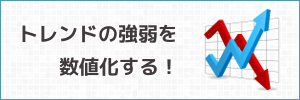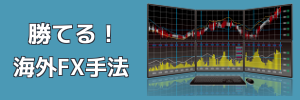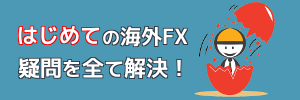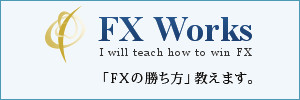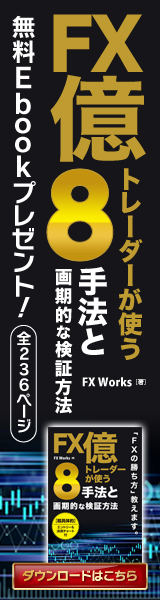現地6月7日から9日にかけての取引では50ドル以上で推移していたNY 原油は、現地6月10日の取引で反落に転じて50ドルを割り込んだ後は、時折持ち直す足取りを見せながらも、大勢的には下降トレンドを描きながらの推移となっています。 この下方を目指す動きは7月下旬を迎えてからさらに強まりました。現地8月2日の取引では中心限月である9月がついに40ドルを割り込んで39.51ドルで取引を終えています。 一時は上昇する足取りを見せていたNY 原油が再び下落指向を強めた背景には、米国内エネルギー供給の過剰感があります。 米国エネルギー省(DOE)エネルギー統計局(EIA)の発表によると、現地7月22日時点の米国内の原油在庫量は、前年同時期に比べて6,150万バレル多い5億2,110万バレルとなっています。また、ガソリン在庫量は前年同時期比で+2,550万バレルの2億4,150万バレルに達しているのです。 今年に入ってからのエネルギー在庫は、供給過剰感が強まった前年度をさらに大きく上回る状態での推移が続いています。そのため、日増しに供給過剰に対する懸念が深まる状況にあり、これが価格の低迷を招いているのです。 それにもかかわらず、6月上旬に価格が上昇する場面が見られたのは、米国での夏場の需要期入りに加え、ナイジェリアでの石油生産施設に対する攻撃とこれによる同国の供給障害に対する警戒感が背景となっていました。 しかしながら、1年で最も需要が拡大する夏場を迎えているにもかかわらず、米国内のガソリン在庫が期待していたほどの縮小を見せず、荷余り感が強いなかでシーズン終了が視野に入ってきていることが、原油価格40ドル割れという事態を招いているのです。 さらに注目されるのが、今夏のガソリン在庫の拡大が需要の減少によってもたらされたものではない、と言う点です。 同じくEIAの発表からシーズン入りした6月1日以後の米国内のガソリン需要(日量)の推移を比較してみましょう。今年度の需要は、6月第1週時点が前年同時期の960万バレルを下回る956万8,000バレル、そして6月第4週時点の需要が前年同時期の973万1,000バレルに対し970万9,000バレルにとどまった以外は、前年同時期の水準を上回る状態が続いています。 それにもかかわらず、在庫が拡大している理由として考えられるのが、供給量の増加です。実際、今年は5月以降、1日当たりのガソリン生産量が1,000万バレルを超える週がたびたび見られるなど、生産量が拡大していることが確認できます。 なお、このガソリン生産量の拡大に関し、EIAではガソリンと中間留分の価格差拡大を受けて、利ザヤを得るために世界的にガソリン生産量が拡大したことが、ガソリンの在庫拡大を促す大きな要因となっていることを指摘しています。 この状況は、この間の中間留分の生産量が前年同時期を下回る状態が多く見られていることからも窺うことが出来ます。なお、この間の原油生産量も減少しているうえ、いかにガソリンに傾倒して石油製品生産が行われていたか、を垣間見ることが出来ます。 しかしながら、すでに8月を迎えてドライブシーズンの終了が視野に入ってくるなか、注意が必要になってくるのは、今後はガソリン生産量は減少に向かう可能性が高い、と言う点です。一年で最もエネルギー需要が増加する時期を終えることに加え、ガソリンと中間留分の価格差が縮小していること、そして、中間留分生産量へと生産がシフトしていくとの見方が根拠となっています。 このような中間留分への生産シフトは、ガソリンの在庫縮小を促すことになるでしょう。これに伴い、石油製品の在庫に関しては供給過剰感が和らぐ可能性があります。 また、原油に関して、6月に経験したように、主要産油国であるナイジェリアでの石油生産施設に対する武力攻撃など、主要産油国において供給障害が発生するというリスクも残されています。 原油に生産障害が発生し、原油在庫縮小見通しが強まるようであれば、エネルギー全体の在庫過剰懸念も和らぎ、これが価格を下支えする要因になってくることが見込まれます。 なお、ブルームバーグ社の調査によると、OPECの7月の産油量(日量)は前月に比べて13万バレル拡大した3,324万バレルとなっています。このような主要生産国による産油量の拡大は、市場の弱気ムードを高める一因となります。 しかしながら、需要面においては世界銀行が今年第1四半期の世界のエネルギー需要は前年同時期比で1.7%増、そして第2四半期は同1.5%増となっていることを明らかにするなど、世界的な需要の増加が伝えられています。 また、一方の供給面に関しては米国における8月のシェール・オイル生産量をEIAは前年同月に比べて14%減少した455万バレル(日)にとどまることが見込まれています。ちなみに米国のシェールオイル生産量が前年同月を下回るのは、9ヶ月連続のこととなります。原油価格の低迷に伴い、供給の調整が進んでいる様子が窺われます。 このように需要が増加すると同時に供給が縮小することで、世界的なエネルギー需給は緩やかながらも引き締まる方向に向かっていると考えられます。 さらに、40ドルを割り込んだことでNY原油市場では安値目標達成感が強まる可能性もあります。 もちろん、夏場のドライブシーズンが終了すれば、秋以降は暖房用としての中間留分の需要期を迎えることになるため、今冬の寒さがどの程度の厳しさとなるのか、といった天候リスクを抱えている点には十分な留意が必要です。 しかしながら、予想を上回る暖冬になるなど、大幅な需要の減少が見込まれる天候が広がらない限り、世界的な需給引き締まりの流れには変化がないと見られます。需給引き締まりに対する意識の強まりは、エネルギー価格の下値を固めることになりそうで、下値を固めた後は年後半にかけてはジリジリと値位置を切り上げる、という展開になってきそうです。 【ご注意】本ブログに掲載されている情報の著作権は株式会社日本先物情報ネットワークに帰属し、本ブログに記載されている情報を株式会社日本先物情報ネットワークの許可無しに転用、複製、複写することはできません。
40ドル割れのNY 原油市場、今後の方向性を探る
[紹介元] コモディティレポート | Klug クルーク 40ドル割れのNY 原油市場、今後の方向性を探る