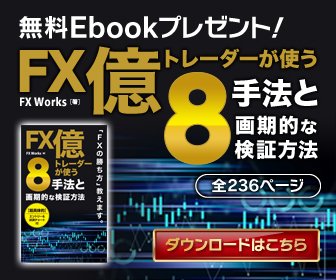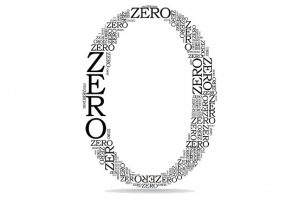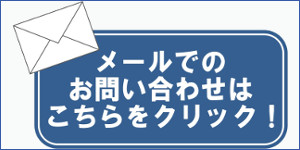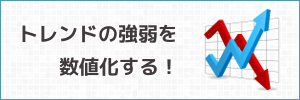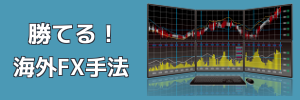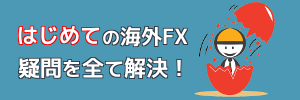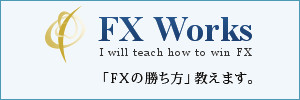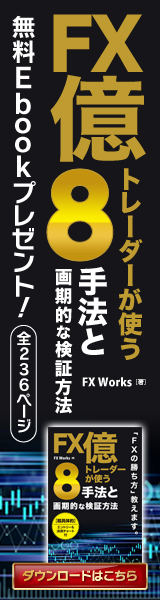CBOT市場では、大豆市場がときおり弱含む動きを見せる一方、コーン市場は大幅安場面を演じるなど、この2つの市場の変化が明白になっています。 この両市場は共に3月の下旬まで低迷場面を演じていました。その後、南米諸国の高温乾燥によるアルゼンチン、ブラジルの生産量予測下方修正を受けて、6月上旬にかけて揃って上値を追う足取りを演じていたのです。 両市場ともに6月下旬まで強い足取りを維持していましたが、それ以降、方向性の違いが決定的となりました。そのきっかけとなったのが、現地6月23日に行われた英国でのEU離脱を巡る国民投票です。 本投票において、英国でEU離脱派が勝利したことがサプライズとなるなか、金融市場ではリスク回避の動きが活発化し、穀物市場においても資金の流出が見られました。しかしながら、離脱派勝利のショックを織り込んだ後、大豆市場が再び上値を目指す動きを見せる一方、コーン市場は下方への方向性を一段と強めました。その背景となったのが、米国農務省が発表した作付報告です。 現地6月30日に米国農務省(USDA)は作付報告を発表しました。3月末に発表される作付意向は、この春に作付する予定を農家から調査したもので実際の作付け面積の予測の基準値にはなるものの予測の範囲に留まります。 これに対し、6月末に発表される作付報告は今春、実際に作付が行われた面積の報告となります。そのため、この作付報告は今秋の生産量を予測するうえで無くてはならない発表であり、最重要視される報告の一つでもあるのです。 それでは、実際に発表された作付面積と作付意向との差がどの程度だったかを見てみましょう。 USDAの発表によると、コーンの作付面積は作付意向の9,360万エーカーに対し9,415万エーカーとされました。また、大豆の作付面積は、作付意向の8,224万エーカーに対し8,369万エーカーと発表されています。つまり、大豆、コーンの作付面積は共に作付意向を上回っていたわけです。 これはどちらにとっても弱材料といえるでしょう。それにもかかわらず、作付面積の発表以降、大豆とコーンの足取りに変化が見られたのはなぜでしょうか。 それは、4月、5月の南米諸国の高温乾燥の影響を受けて、大豆価格が高騰するなか、大豆へと作付がシフトし、その結果としてコーンの作付面積は縮小するのではないか、との見方が広がっていたことが考えられます。 なお、この間、コーン価格は大豆と同様に上昇していました。しかしながら、比価で見た場合、大豆の方がコーンに比べると割高と考えられていました。これを受けて、コーンから大豆へと作付がシフトするとの見方が強まっていたのです。 4月以降の大豆、コーンとの比価を見てみると、価格急落のきっかけとなった6月23日直前までの間、比価は適正とされる2.3(大豆がコーン価格の2.3倍)に対し、最も低くて2.50、高い時には2.85に達しています。この推移から、大豆がコーンに対して常に割高な状態にあったことが窺われ、これこそが、大豆への作付けシフトを促すとの見方の根拠となっていたのです。 しかしながら、今回発表された作付面積は、CBOT市場でコーン価格が400セントを超える強い足取りを見せるなか、米国内ではコーンに対して強い作付け意欲が見続けられたことを明らかにしました。 このように作付面積がこれまでの予測を上回ったことを受けて、米国のコーン生産量予測も上方修正される可能性が高まっています。 6月発表の需給報告の作付面積に対する収穫率とイールドが示現されると仮定した場合、生産量は145億2,000万ブッシェル程度に達することが見込まれます。約9億ブッシェル程度、生産量が引き上げられる可能性が出てきているわけです。 また、同時に発表された四半期在庫量も市場予測の45.28億ブッシェルを大幅に上回る47.22億ブッシェルと弱気な内容だったことが、追い打ちをかけています。 今後、輸出用を含めた需要がどう修正されるのか、そしてシルキング~デント期の米国中西部のコーン産地の天候がどうなるのか、というポイントが残されています。しかしながら、すでに6月の需給報告では南米の生産量下方修正を受けた米国のコーン輸出量予測の上方修正が行われる一方、国内需要の弱さが目立つ状況にあるだけに、大豆に比してコーン市場はしばらく低迷場面を強いられることになりそうです。 【ご注意】本ブログに掲載されている情報の著作権は株式会社日本先物情報ネットワークに帰属し、本ブログに記載されている情報を株式会社日本先物情報ネットワークの許可無しに転用、複製、複写することはできません。
大豆市場とコーン市場、明暗を分けた原因は何か
[紹介元] コモディティレポート | Klug クルーク 大豆市場とコーン市場、明暗を分けた原因は何か