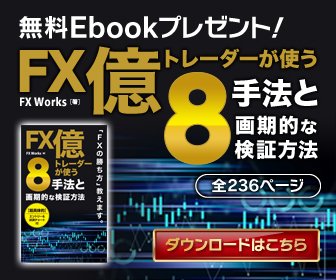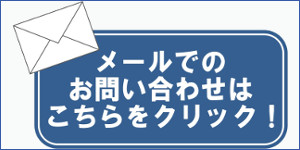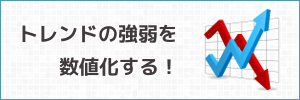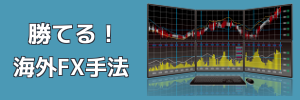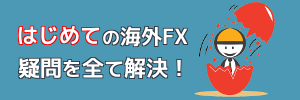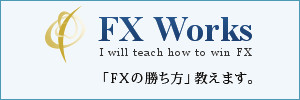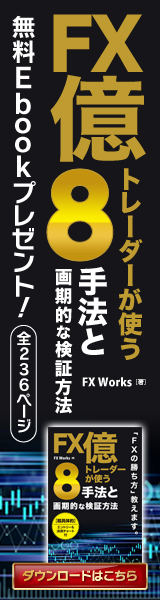仮想現実(VR)の動画で途上国の暮らしを体感してほしい。そんなプロジェクトに、若手作家や写真家らの有志グループが乗り出した。グループは「日本の子どもたちが世界の問題と向き合うきっかけになれば」と教育での活用を目指している。 (伊藤弘喜)
グループは「セカイ・メディアラボ」。東南アジアやアフリカ、中東などで貧困や紛争を取材してきた作家の石井光太(こうた)さん(39)とフォトジャーナリストの安田菜津紀(なつき)さん(29)=どちらも東京都内在住=が中心。編集者らを加えた計五人で三月に本格始動した。
石井さんが三年前、「世界の貧困」をテーマにした博物館をつくりたいと発案したのがきっかけ。大きな問題なのに日本では直接知る機会が少ない、という問題意識があった。
だが、ハコものを造るのは厳しい。そこで目を付けたのがVR動画。石井さんは「普通の動画や写真より、強烈な体験が得られる。この動画で小学校などで出前授業をすれば、関心を持ちやすいのでは」と話す。
VRの専用カメラは三百六十度、全方向を撮影。専用ゴーグルに動画を取り込んで装着して視聴する。すると、上下左右を向いたり、振り返ったり、頭の向きに応じた風景が目の前に広がる。動画の中を自由に動いているかのような臨場感を味わえる。
第一弾は、過激派組織「イスラム国」の台頭でテロや宗派対立が続くイラクで撮影する。訪問先に予定しているのは北部のクルド自治区。治安は比較的安定しているが、国内の他地域からの避難民や隣国シリアからの難民を多く受け入れており、財政難や物資不足に苦しんでいる。
だが撮影では「悲惨さだけを描くことはしない」という。石井さんは「紛争が起きている中でも恋愛があり、結婚式があり、誕生日会がある。私たちと共通する現実をVRで見てほしい」と力を込める。
石井さんと安田さんは、イラクで支援活動に取り組むNPO法人「日本イラク医療支援ネットワーク」の協力を得て、来年一月にも撮影に入る予定。
◆医療、物件探し…広がる用途
仮想現実(Virtual Reality=VR)を楽しめる専用ゴーグルが相次いで発売されている二〇一六年は「VR元年」と位置付けられる。
VR用ゴーグルは一九八〇年代に米国で登場したが高価で映像の質が低かったため、廃れた。しかし、近年、高性能なものが消費者の手が届く価格となり、再び注目を集めている。
さまざまな分野で活用が広がりつつある。米航空宇宙局(NASA)の全面協力の下で開発された火星有人探査の体験ゲームが年内に登場。欧米では外科手術や軍の訓練でも活用されている。住宅業界では物件をVRで体感できるサービスがスタート。報道の分野にも活用の場が拡大し、世界のVR市場は二〇年には七百億ドル(約七兆円)に達するとの予想もある。
主な専用ゴーグルの価格は、七月に発売した台湾の電機大手、HTCが約十万八千円。ソニーは今年十月に約四万九千円で発売する。一方、スマートフォンと組み合わせる簡易ゴーグルは千円前後からある。
◆東京の作家ら資金募る
インターネットで資金を募るクラウドファンディングで機材や渡航費用500万円を募っている。1口3000円から。特製ハガキやVR動画の試写会などの特典がある。進行状況はフェイスブック(https://www.facebook.com/sekai.medialabo/)で紹介している。
[紹介元] 東京新聞 経済面 紛争や貧困 自分の目で 仮想現実 日本の子に