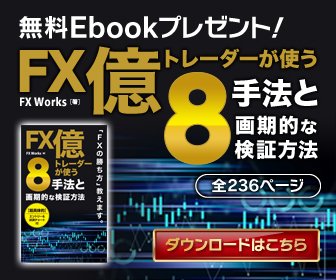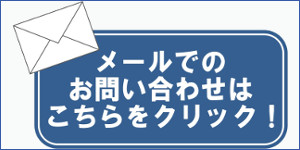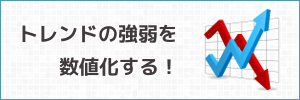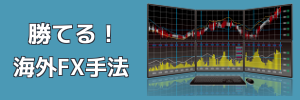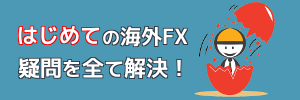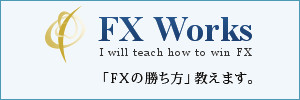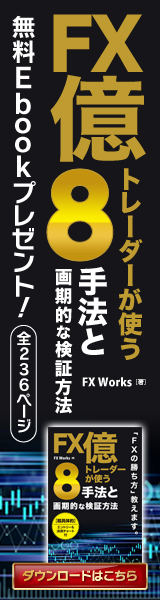本連載は、今回が最終回となる。 本連載開始時点から、筆者は財務省やマスコミが撒き散らす「日本の財政問題の嘘」について批判することを続けてきた(ちなみに、第1回のタイトルは「日本の財政問題に関するマスメディアのミスリード」であった)。 我が国は、1997年の橋本緊縮財政以降、二十年近くもの間、国民が貧困化するデフレーションに苦しめられている。何しろ、国民の実質賃金はピークの1997年と比較し、何と13%も下がってしまったのだ。我々は、97年時点の日本国民よりも13%「貧乏」なのである。 デフレーションは、国民経済における「消費」「投資」という需要が不足することで発生する。細かい話を書いておくと、バブル崩壊で国民が借金返済、預金を増やし、反対側で消費や投資という需要が停滞している時期に、政府が緊縮財政を強行するとデフレーションになる。国民が消費や投資を減らし、誰かの所得が減っている状況で、政府までもが消費増税で国民の消費を抑制し、更に自らも投資(公共投資)を減らすのだ。国民経済の総需要不足は深刻化し、物価と所得が悪影響を与えながら共に下落していくデフレーションに突っ込む。 過去の日本において、総需要を拡大するという「正しいデフレ対策」を実施した政権は、あるにはあった。ところが、政府が財政出動で総需要を創出しようとすると、途端に、 「国の借金で破綻する! 増税だ! 政府は無駄を削れ!」 といった「嘘」の大合唱が始まり、結局、財政拡大は中途半端に終わり、消費税も増税され、日本国はデフレの呪縛から逃れられない状況が続いてきた。 「デフレ脱却」 を標榜して誕生したはずの安倍政権は、13年度は金融政策と財政政策のパッケージという正しいデフレ対策を実施した。ところが、14年度以降は消費税を増税し、政府は緊縮に逆戻り。デフレ対策は日本銀行に丸投げされたわけだが、一向に物価や所得が上向かない状況が続いている。 直近データである16年4月のインフレ率(コアCPI)は▲0.3%であった。200兆円を超す日本円を発行したにも関わらず、インフレ率がマイナス。 我が国において、消費や投資という「需要」が不足していることは、誰の目にも明らかなのだ。不足しているのは総需要であり、おカネではない。 デフレは「貨幣現象」とやらではなかったのだ。 所得(実質賃金)に目を向けると、15年度もやはりマイナス。相も変わらず、国民の貧困化が続いている。 【図 日本の実質賃金の推移】 出典:厚生労働省 さすがに、日本の総需要不足を否定する政治家は、最近は消滅しつつある。問題が総需要不足である以上、民間最終消費支出という「需要」を抑制する消費税増税は、決して実施してはならない。 2014年4月の消費税増税は、14年度の民間最終消費支出を実質値で2.9%も減らした。日本の民間最終消費支出は300兆円規模であるため、2.9%のマイナスは、10兆円前後の需要抑制効果があったという話になる。 内閣府の計算するデフレギャップは、例により「平均概念の潜在GDP」を使っているため、実態より小さく出るが、それでも直近の需給ギャップは対GDP比で▲1.6%。つまりは、金額にして8兆円規模のデフレギャップがあると、政府自ら認めているのだ。 無論、13年度の民間最終消費支出には、14年3月の駆け込み消費分が含まれている。とはいえ、消費税増税が強行されなければ、民間最終消費支出が「減らない」ことで、対GDP比▲1.6%のデフレギャップが埋まっていた可能性が高いのだ。 とにもかくにも、14年4月の消費税増税が諸悪の根源なのである。 「アベノミクスでデフレ脱却!」 「経済最優先!」 などと三年もやっておきながら、インフレ率が目標の2%に届くどころか、▲0.3%という惨状をもたらした主犯は、文句なしで14年4月の消費税増税なのだ。 本連載が掲載される6月1日には、結果が明らかになっているだろうが、安倍総理はどうやら17年4月の消費税再増税は「延期」する模様である。また、財政出動についても「拡大」に舵を切り直すと思われる。 『2016年5月28日 産経新聞「消費税増税2年半延期 安倍首相が麻生、谷垣氏らへ方針伝達 麻生氏は「解散」主張」 http://www.sankei.com/politics/news/160528/plt1605280037-n1.html 安倍晋三首相は28日夜、首相公邸で麻生太郎副総理兼財務相、自民党の谷垣禎一幹事長、菅義偉官房長官と会談し、来年4月に予定している消費税率10%への引き上げを平成31年10月まで再び延期する方針を伝えた。国会会期末の6月1日にも発表したい考えで、政府・与党内の調整を急ぐ。 会談で首相は、消費税率の引き上げを「2年半延期したい」と伝えた。これに対し、麻生、谷垣両氏は財政規律維持の観点から予定通りの増税を求めて異論を唱え、引き続き協議することになった。 麻生氏は「再延期するなら衆院を解散して国民の信を問うべきだ」とも主張した。首相は同調せず、菅氏は公明党に配慮して衆参同日選を見送るべきだとの考えを示した。 連立与党の公明党も社会保障の財源確保のため再延期には否定的な立場をとってきた。首相は近く、同党の山口那津男代表とも会談して理解を求める。』 消費税の再延期に、衆院解散は不要であろう。何しろ、野党第一党(民進党)も二年の延期を主張しているわけだから、国会で法案を通せば済む話だ。 また、社会保障の財源確保は、短期的には「税収弾性値」により増加した税収を、中期的には赤字国債を、長期的には経済成長による税収増を充てるべきだ。消費増税再延期に伴い、財政出動も拡大し、日本のデフレ脱却が早期に実現すれば、赤字国債の発行額もそれほど増えない。 むしろ、増税や財政出動の絞り込みを続け、デフレが長引いた方が、名目GDPが成長せず、税収も減り、社会保障の財源も赤字国債以外には確保できなくなる。 それにしても、未だに「財政規律維持の観点」などという発言が与党幹部から出てくるわけだから、呆れ返ってしまう。 政府の目的は「国民を豊かにする」経世済民であり、財政規律の維持ではない。財政規律が維持されたとしても、国民が貧困化してしまうのでは、政治家失格だ。 そして、まさに14年度、15年度の安倍政権は、財政規律(プライマリーバランス)とやらに縛られ、緊縮財政を強行し、国民を二年度連続で貧困化させた。実質賃金が下がり、民間最終消費支出の実質値が二年度連続で下落。 国民を二年度連続で貧困化に叩き込んだ政権は、統計的に確認できる55年以降、安倍政権が初めてだ。 改めて振り返っても、財務省や政治家たちの「財政規律維持」へのこだわりは、異様である。とはいえ、経済学的には異様ではない。 経済学という学問的には、借金は「所得」から返済する必要があるという話になっているのだ。 借金をしているのが「個人」であれば、一応、借金は返済する必要がある。理由は、個人という人間には寿命があるためだ。 「人間は寿命がある以上、一生涯に稼ぐ所得以上の借金をしてはならない。生涯所得が、個人が借り入れられる負債総額の限界となる。」 上記の考え方を、経済学において「予算制約式」と呼ぶ。予算制約式は、「経済人」などと同様に、経済学の前提の一つだ。 予算制約式とは、「個人は一生に稼ぐ所得以上の支出はできない」という原則になる。予算制約式で個人の負債拡大の「枠」を設定しない場合、経済学は美しい数式モデルを構築できなくなってしまうのだ。予算制約式は、経済人と同じように、経済学が「学問」として発展するために必要だった、前提の一つなのである。 困ったことに、経済学者たちは「個人」の場合は、ある程度の合理性がある予算制約式を、政府にまで適用しようとする。予算制約式に基づくと、政府は「税収に見合う支出しかしてはならない」という、いわゆるプライマリーバランス理論が正当化される。あるいは、国債の返済は「税金で」という理論もまた、正しいという結論になってしまうのだ。 とはいえ、政府と個人は違う。何しろ、個人は有限だが、政府は無限なのだ。 さらに、政府には「通貨発行権」という強力極まりない権限が存在している。現実に、日本銀行が年に80兆円という凄まじいペースで日本円を発行し、国債を買い取り、政府の実質的な借金がピークの2012年9月比で130兆円も減った我が国が、「財政規律」とやらに足を取られ、国民貧困化を続けるなど、狂気の沙汰としか言いようがない。 日本政府は「財政規律」などという個人の家計簿発想から脱し、正しいデフレ対策を打たなければならないのだ。 とはいえ、6月1日に安倍総理が「消費増税の二年延期」「財政出動の拡大」を表明した場合(それ以前からだが)、 「財政の効果は一時的だ!」 「公共事業を増やしたところで、短期の話で終わる」 などと、カビの生えた財政出動否定論がマスコミに登場し、日本のデフレ脱却を妨げることになるだろう。この手のレトリックには、二つ、明確な間違いがある。 一つ目は、例えば交通インフラの整備一つとっても、プロジェクトは数年、十数年は続くという話だ。北陸新幹線の敦賀延伸の開業予定は2023年であるため、東京五輪の三年後だ。 北陸新幹線の敦賀-大阪間について、早期にルートが決定し、事業化したとしても、さすがに2023年までに完了させるのは難しいだろう。ということは、今から七年間はプロジェクトが継続することになる。 リニア新幹線に至っては、JR東海が東京-名古屋間を2027年までに建設する予定になっている。自民党の議連が、2045年(!)に予定されている名古屋-大阪間の開業を早めるべく動いているが、それでも目標は2030年だ。 すなわち、リニア新幹線を大阪まで早期開業することが決定したとしても、今から14年間はプロジェクトが続くことになる。 交通インフラの建設が「短期」で完了するはずがないだろうに、この手の「現実」は無視して、「一時的だ!」「短期の効果しかない!」などと言ってくる。 更に、そもそも交通インフラの効果は、土木・建設業の所得を生み出すフロー効果に限らない。交通インフラ完成後、人々や物資の流通速度を高めることで、「生産性を向上させる」ことが可能になる。 生産性向上とは、生産者一人当たりの生産(GDP)の拡大効果だ。今後の我が国は、少子高齢化で生産年齢人口比率が低下していく以上、生産性を高める必要がある。そのためにも、将来の生産性向上をもたらす交通インフラの整備は必須なのだ。 現時点で交通インフラを整備することで、 「現在のデフレギャップ(総需要の不足)を埋め、同時に将来のインフレギャップ(生産能力の不足)を埋める生産性向上が達成される」 のである。完璧なソリューション(解決策)と言える。 それにも関わらず、6月1日以降のマスコミでは財政否定論、インフラ整備否定論が撒き散らされ、財政出動を妨害する動きが激しくなるだろう。さらに、相も変わらず、 「財政破綻を避けるために、消費税増税を!」 といった財政破綻論者たちの大合唱も始まる。 日本のデフレ脱却のためには、「財政出動の拡大」「消費税増税の否定」という真っ当な政策が不可欠だ。「正しい言論」の力が、今ほど求められる時代は、そうはないのである。
第360回 日本のデフレ脱却のために(最終回)
[紹介元] 三橋貴明の「経済記事にはもうだまされない!」 | Klug クルーク 第360回 日本のデフレ脱却のために(最終回)