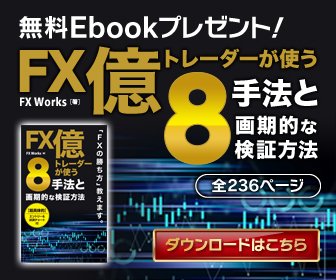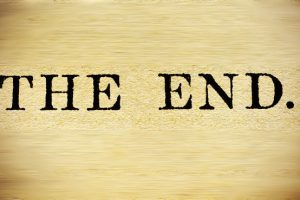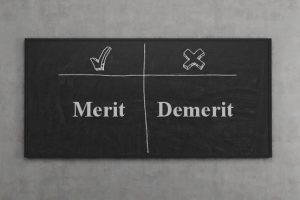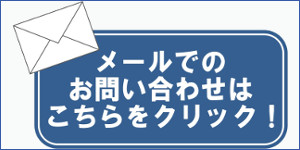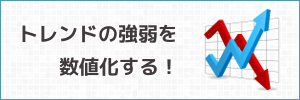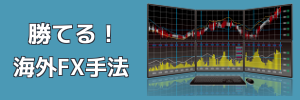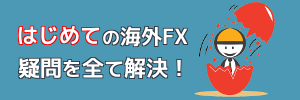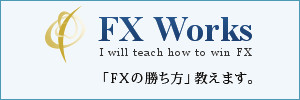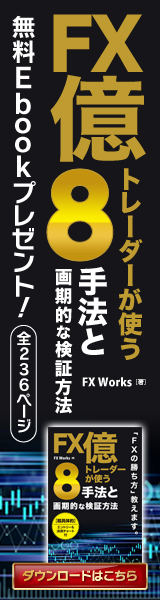(1/3)から続く もっとも、「成功させる会」は、肝心要の消費税については「増税して凍結」という、間違った提言となっている。提言書では、消費税増税について、現在の消費低迷の原因であることを認め、さらにデフレギャップが10兆円近くあることも認識している。 アベノミクスを成功させる会では、先日、内閣官房参与である藤井聡京都大学大学院教授が、安倍政権が掲げた名目GDP600兆円の目標を達成するために、 ●増税延期 ●政府は「所得ターゲット」政策を改めて宣言すべし ●政府はデフレ完全脱却こそが最大の財政健全化策、と宣言すべし ●「脱出速度」確保のための、3年限定の積極財政を ●デフレ脱却後は、PBでなく債務対GDP比を基準とした中立的財政を を提言した。藤井教授の提言通りにしておけばいいものを、それでも「予定通り増税」とやってくるわけだから、話にならない。 本質的におかしいのだが、少なくとも「成功させる会」の山本会長らは、 「デフレは総需要の不足である」 を、理解しているはずなのだ。総需要の不足が問題である以上、財政出動による需要創出は当然として、民間最終消費支出という需要を縮小させる消費税増税は「決してやってはならない」政策になる。 総需要の拡大を訴えながら、総需要縮小策を提言するのでは、整合性が全くない。 「成功させる会」の提言書では、現在の景気低迷について、 『当初(2014年)の引上げ(5%→8%)時の財政出動が十分でなかったこと、年金生活者や低所得者の実質所得が低下したこと、そして「いずれ消費税率は上がるのだから」という予想から消費が抑制された面があること等にあった(「提言」より引用。以下同)』 と、分析されている。 14年の増税の際には、財政出動が不十分だったため、消費の長期低迷を招いた。ということは、次なる増税の際には、十分な財政出動により、消費の落ち込みを防ぐことができる、という理屈だ。 根本的に間違っているわけだが、消費税増税の影響は無制限に続く。それに対し、補正予算による財政出動は一時的措置に過ぎない。 永続する悪影響を、一時的な給付金でカバーできるはずがない。 今回の提言では、消費増税の悪影響を軽減するために、財政出動を「三年」継続するように求めている。とはいえ、断言しておくが、上記の提言に従い、16年度にある程度の財政出動を実施し、17年4月に増税をすると、途端に財務省配下のマスコミから、 「財政破綻! 国の借金で破綻する!」 の大合唱が起き、17年度、18年度の財政出動は削減され、消費税増税「凍結」の約束も破棄されることになる。 財務省の官僚が数百人体制で政治家、マスコミ、学者たちに「ご説明」に回り、再び「増税やむなし」「緊縮やむなし」の空気が作られ、再び消費税増税、財政支出削減の緊縮財政が始まる。 財務省にしてみれば、とりあえず17年4月の増税を実現できれば、 「悪影響を防止するための財政出動」 や、 「その後の消費増税の凍結」 については、後から何とでもできると考えているのだろう。 財政出動は16年度のみで、17年4月の増税が実現され、その後、緊縮に転じるという未来が、間違いなく待ち受けている。 逆に言えば、上記の提言から「増税を実施する」の部分のみ回避できれば、全体的にはデフレ脱却のために適した政策ということになる。財務省は消費税増税と引き換えに、その他のデフレ対策については認めた、という話なのだ。 (3/3)へ続く
第359回 「アベノミクスを成功させる会」の提言 (2/3)
[紹介元] 三橋貴明の「経済記事にはもうだまされない!」 | Klug クルーク 第359回 「アベノミクスを成功させる会」の提言 (2/3)